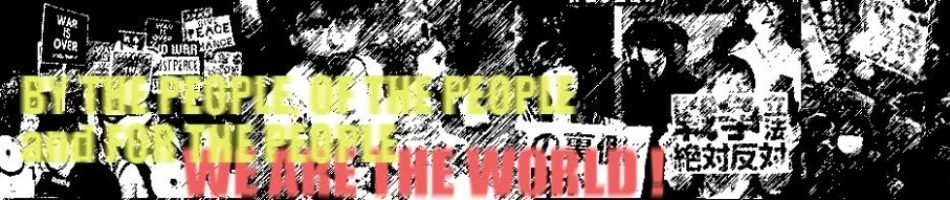
ホーム » エッセイ » 【 2011年東日本大震災の被災地の4年後 】《後篇》
被災者のつらく厳しい時間は、まだまだ終わることなく続いている
極めて多くの復興事業が必要なのに、予算を使い切れずに返してしまうなどあまりに馬鹿げている
巨大防波堤を築くような大規模公共事業のためには喜んで機能する日本政府も、一般庶民を救済するためにはほとんど機能しない
マーティン・ファクラー / ニューヨークタイムズ 3月12日

日本政府は2016年に終了予定の被災地復興と福島第一原発事故による放射能の除染作業を柱とする『復興集中事業』を継続・支援するため25兆円の追加出資を表明しました。
しかし地方自治体では復興事業のための課題や事務処理が山積し、多くが当初の予定より大幅に遅れ、そのため用意された復興予算が使いきれずに残ってしまう事例が数多くみられます。
大槌町がそのよい例です。
大槌町はごつごつした岩山を背に太平洋を望む絵のように美しいリアス湾に、住民15,200人が暮らす静かなコミュニティでした。
その大槌町を襲った津波の高さは15メートルを超え、町役場、消防署、警察署、基幹病院を含む町の建物の8割を破壊するというすさまじい威力を見せつけました。
この津波のせいで市職員約50名と市長も命を落とし、大槌町では東日本大震災発生後数カ月間、首長のいない状態が続いたのです。
「町は完全な混沌状態に置かれ、あらゆる機能がマヒしてしまいました。」
新任の町長である碇川豊氏が仮設町役場でのインタビューでこう語りました。
仮設町役場は現在、東日本大震災で被災した小学校の校舎内にあります。

大槌町の被災者は仮設住宅が完成し、水道や電気などのライフラインが復旧するまで1年もかかったと証言しました。
総計50万トンにもなったつぶされた自動車、粉々になった樹木、その他のがれきの片づけが完了したのは、やっと昨年になってからの事でした。
そして生き残った人々の間では、具体的にどのような大槌町を再建したいのかという点において、合意形成は非常に難しいものになりました。
一部の人々は、日本政府当局が提案した多額の経費をかけた巨大な防波堤の建設に賛成を表明しました。
しかしそんな防波堤も他の被災地では人々の命を救う事が出来なかった事実を指摘し、反対する人々もいました。
これらの人々は、完璧な津波対策とは、高台に町を再建することだと主張しました。
結局、町の再建計画は妥協の産物になりました。
すなわち、かつての町の中心部の土地をかさ上げした上に工場や商店街などの商工業施設を建設し、その周囲をサッカー競技場の半分程度の大きさの基礎を打った防波堤で囲い込むのです。
そして大部分の住民は丘の頂上を削って新たに造成する箇所も含め、高台に住宅を建設・移転することになったのです。
現在津波によって平らにされてしまった被災地は、新たに運び込まれた土砂によって分厚く覆われています。

津波に襲われた際にほぼ完全に水没した3階建てのコンクリート製の町役場は、中身をすっかりさらわれてしまい、今は町の中心部に残骸を残すのみになってしまいました。
その前に一体の仏像が安置され、この場所で亡くなった人々の霊を慰めています。
しかし皮肉なことに、復興事業の開始とともに新たな遅れが発生することになりました。
東北太平洋岸地区における復興事業本格化とともに、一帯における建設作業会社の不足が深刻化し、大槌町では競争入札に応札する業者の確保すらままならない現実に行き当たりました。
この業者の不足は、東京でオリンピック関連の建設事業が始まったことにより、なお一層悪化していると碇川町長が語りました。
この結果、大槌町は日本政府から割り当てられた復興資金を使い切ることができませんでした。
2012年、大槌町は割り当てられた200億円の復興事業資金のうち、28パーセントしか使うことはできませんでした。
昨年、新しい再建策が実行に移されて予算の62パーセントを使う事が出来、多少なりとも状況が改善したと碇川町長が指摘しました。

「町が極めて多くの復興事業を行う必要があるのに、割り当てられた予算を返してしまうなどあまりに馬鹿げています。」
地元の地区委員長の委員長を務める、津波で自宅が流出した佐々木恵一さん(53歳)がこう語りました。
現在3,700人の住民が自宅の再建を待ちながら仮設住宅暮らしをしています。
しかし数千人の人々が町内での再建をあきらめ、町を出ていきました。
大槌町役場は、東日本大震災とそれに続いた人口流出により、町が4分の1の住民を失ってしまったものと試算しています。
町役場勤務を引退した川口さんは、町を去った人々の数は実際にはその試算を上回っている可能性があると考えています。
復興事業とオリンピック関連建設事業の本格化による建設ブームのおかげで、建設労働者と建設資材の値上がりが続き、今や住宅建設費用が2年前の倍以上になってしまっているのです。
こうした状況を解消するために、日本政府はほとんど機能していません。
自宅の再建には3,600~4,800万円ほどが必要ですが、政府の支援は480万円から720万円ほどです。

「日本政府は巨大な防波堤を築くような大規模な公共事業のためには喜んで機能しますが、一般庶民を救済するためにはほとんど機能しないのです。」
川口さんがこう語りました。
「復興事業が長引けば長引くほど、私たちの町の衰退はなおさら進んでしまうのです。」
〈 完 〉