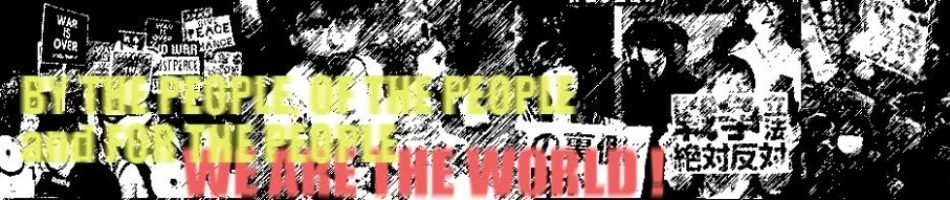
ホーム » エッセイ » 【 減り続ける日本人・子供の人口38年連続で減少 】
制度的にも社会的にも女性たちをサポートしない日本、増える負担・減少する出生数
地域が子供を守り育てるというシステムが消滅、その分の負担がもろに若い両親に

山口まり / AP / ワシントンポスト
日本の子供の人口は38年連続で減少し、現在その人口は過去最低を記録していると、4日土曜日日本政府が公表しました。
統計局によると、日本の15歳未満の子供の数は2019年4月1日時点で1,152万人で、前年と比べ18万人(1.2%)減少しました。
このデータは5月5日のこどもの日を前に発表されました。
家事、そして伝統的に女性の仕事とされている様々な雑用などの負担を背負わされている日本の働く女性たちは、長時間労働と高額な教育費という問題に直面させられていますが、制度的にも社会的にもサポートしてもらうことができないため、日本の出生率は低水準に留まっています。
統計局が公表した数値によれば、日本の人口に占める子供達の割合はの12.1%と、人口が4,000万人を超える国々の中で最低です。
ちなみに韓国は12.9%、イタリアとドイツは13.4%です。

2017年の時点で、日本人女性は生涯の間平均して1.43人の子供を産みました。
比較すると、英国と米国の平均は1.8人です。
最新の政府統計によると、2018年の出生数は日本が1899年に出生者数を記録し始めて以降、最低の921,000人に減少しました。
日本の総人口も448,000人減少して1億2,600万人になり、過去最高の減少数を記録しました。
日本の人口は大量の移民の受け入れなどが行われなければ、2050年までに1億人を下回ると予測されています。
深刻な労働力不足が拡大する日本は先月、法的規制を緩和してより多くの外国人労働者の受け入れを開始しました。
安倍首相は、高齢化と低出生率は国家的危機であると述べ、夫婦がより多くの子どもを持つことを妨げている家族の負担を軽減するため、労働問題その他の改革を約束しました。
日本の長寿命化は、高齢者介護や社会保障のためのコストの上昇を招いています。
安倍政権の保守的な議員たちは長期的な人口現象の責任について、ことあるごとに高齢者や子供のいない人々を非難してきました。

湿原の多さで知られる麻生太郎財務大臣は今年初め、社会保障費の高騰と人口減少の責任は子どもを作らない人間たちにあると発言し、謝罪する羽目に陥りました。
https://www.washingtonpost.com/Japan child population falls for 38th year, hits postwar low
+ - + - + - + - + - + - +
日本の少子化については、地域が子供を守り育てるというシステムがいつの間にか日本の社会から消滅してしまったことが原因として大きいのではないか、と思います。
昔のことを言っても仕方がないかもしれませんが、私が子供だった昭和30年代〜40年代というのは、間違いなく地域が子供たちを見守ってくれているという実感を子供ながらに感じていました。
私は仙台駅から徒歩10分〜15分といった場所で子供時代を過ごしましたが、街中や路上で何かトラブル(現代の定義のような深刻なものではなく、飽くまで子供にとってのという意味の)に見舞われると、必ず近くにいた大人が手を貸してくれて助けてくれました。
しかし今は子供に知らない大人が近づくと、別の心配をしなければならない時代になってしまいました。
その分、若い親の双肩にかかる負担も大きなものになっているのでしょう。
一方で子供が可愛いと感じる、まだまだ元気な高齢者がたくさんいます。現実に学校の登下校時の見守りなどをされている方も多数いらっしゃいますが、それだけでは若い親ごさんの負担の軽減にまでは繋がないでしょう。
一定時間内なら勉強を手伝ったり、情操教育をしたり、スポーツを教えたり、あるいは食事の世話だってしてあげたいという高齢の方は多数いらっしゃるのではないでしょうか?
若い親ごさんたちも、きちんとしたシステムの下で安心してそういった形で子供たちを見守ってくれるなら、負担の軽減につながるのではないでしょうか?
本来なら行政がそうしたニーズと善意とを結びつける取り組みをしてくれるなら社会はだいぶ住みやすいものになるはずです。
しかし現在の日本の政権を見る限り、そこに多額の金のやり取りが発生しない、地道にコツコツと社会を良くしようという取り組みは、見向きもされないというのが正直な感想です。
そのような政治が続く現状を容認することによって、次の世代、その次の世代の人々をどんどん追い詰める結果につながっているということについて、私たちは深刻に反省すべきなのではないでしょうか?