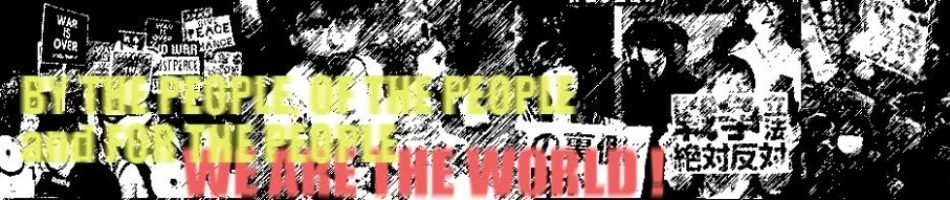
ホーム » エッセイ » 【 『強制的』帰還に直面する福島の被災者たち – 打ち切られる財政援助 】《後篇》
すべての責任を負うべきなのは福島第一原発の事故、しかし被災者に責任が転嫁される状況が作られている
様々な事情など顧慮されることなく、原発事故の被災者に対する補助金が打ち切られようとしている
ジャスティン・マッカリー / ガーディアン 2017年3月10日

松本さんが体験したのは、福島県で暮らしていた何千人もの人々の間で繰り返された運命と同じものでした。
松本さんの夫は松本さんと一緒に、人口330,000人規模の、そして福島第一原発の事故発生の際は誰一人避難命令を受け取ることが無かった郡山市内でレストランを経営していました。
彼は妻が子供たちを連れ神奈川県に避難することを決めたとき、一緒に行ってそこで失業者になるリスクを冒すより、郡山に留まってレストランの経営者を続けることの方を選択しました。
神奈川と郡山を行き来する費用は、決して安くはありません。
松本さんの家族が全員一緒になれるのは2ヵ月に1度だけという状態です。

地元の自治体によれば松本さんの近所で暮らす2人以上の世帯に対する公的な住宅助成金の一般的な金額は、一カ月当たり90,000円です。
この助成金が打ち切られると、一部の世帯は補償金としてもっと少ない金額しか受け取れなくなります。
「本来ならこうした状況に一番責任をとらなければならないのは福島第一原発の事故のはずです。それがいつの間にか責任が転嫁され、まるで私たちの過失であるかのように、私たちが利己的であるかのように言われるようになってしまったのです。」
松本さんがこう語りました。
避難指定区域外から自主的に避難した人々は、これまで住宅に対する公的な補助金が支給されるように運動してきましたが、これはいくつかの地域で除染作業が適切に行われ、安全に居住できるようになったと、より多くの避難者を納得させようとしている行政当局に対し疑問を呈する意義もあります。

国際放射線防護委員会は環境中の放射線量が1年につき1ミリシーベルト(mSv)以下にならない限り、人間の居住には適さないというガイドラインを採用するよう推奨しています。
この基準に基づき福島県の住民の安全を確保しようと取り組んでいる人々は日本政府に対し、環境中の放射線量が1年につき1ミリシーベルト(mSv)以下になった時点で安全宣言を行うように求めてきました。
しかし日本政府は1年につき1mSv以下の放射線量を政府の長期的目標としている一方で、環境中の放射線量が原子力発電所など原子力関連施設で働く労働者と同じ被ばく基準である1年につき20mSv以下になった段階で、かつて住んでいた場所に戻って暮らすことを奨励しているのです。

松本さんは、確かに前例の無い規模で実施された福島県内での除染作業により、彼女の自宅やその周辺の放射線量が20mSv以下になった以下になったことを認めましたが、子どもたちが当然のように出入りする場所、たとえば公園や森林などには極端に放射線量が高い『ホットスポット』がいくつも残され、子どもたちが危険にさらされることになると主張しています。
「こうした場所の除染は未だ済んでいません。」
松本さんがこう語りました。
「大気中の放射線量が盛ったというのは事実です。しかし土地の放射能汚染や土壌中の汚染がすべて取り除かれたわけでは無いのです。」
3月末にはさらに4つの町村の避難指定が解除されることになっていますが、福島第一原発に最も近く放射線量が50ミリシーベルト(mSv)を超える地区に限っては、立ち入りの禁止が継続されることになっています。

福島第一原発の事故が発生し多くの人々が避難を余儀なくされた当初、元住んでいた場所に戻らなければ補償金も補助金も受けられなくなるなどという話はありませんでした。
しかし現在様々な事情など顧慮されることなく補助金が打ち切られようとしています。
そうなれば、多くの被災者が経済的理由から帰還を余儀なくされることになるのです。
〈完〉
https://www.theguardian.com/world/2017/mar/10/japan-fukushima-nuclear-disaster-evacuees-forced-return-home-radiation
+ – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – +
私事ですが、今月仙台市内の国立大の博士課程を修了し、工学博士として国内の精密工作機械メーカーの研究所に勤務することになった長男が、福島県楢葉町出身の女性と婚約しました。
彼女は福島第一原発の事故の時は高校3年生で、実際に家族と一緒に緊急避難を経験したいわゆる原発難民です。
彼女の健康についてまったく懸念が無いはずもありませんが、これからは両方の家族が2人が築く家庭が健康で明るいものになるよう、全力で支えていくだけだと考えています。
しかしこうして身近に原発難民にされてしまった方々の話を聞く機会を得て感じるのは、この人々が本当に必要な情報をすべて提供されているのかという、肌が泡立つような怒りです。
安部首相がオリンピック開催地選定委員会の席上「福島第一原発は『アンダー・コントロール』」と宣言した段階で、ある程度この問題について知識を持った世界中の人々が、事故の隠ぺいと欺瞞工作が行なわれていることを実感したでしょう。
真実が解れば対応のしようもある、解決方法について考えることもできるのです。
最も弱い立場に追い込まれた人々を闇の中に置き去りにする、それが『美しい日本』というものなのでしょうか?
+ – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – +
【 メトロポリタン美術館375,000点の収蔵作品をデジタル化、無料提供 】《14》
ニューヨーク・メトロポリタン美術館
ニューヨークのメトロポリタン美術館はそのコレクションをデジタル化し、無料で375,000点に上る画像データを公開しました。
いずれも公有財産として、無料で制約なしで利用することが出来ます。

パウル・クレー(スイス生まれドイツ: 1879–1940)作[静物](写真上)石膏ボードの上に油彩、1927。
クレーは自身の作品リストについて、気に入った作品にアンダーラインを引いていますが、この作品もその中に含まれています。
そこには「少ないほど豊か」と書き込まれており、クレー自身が静物の形と色を単純化することにより、互いが互いを引き立てるという効果をねらっていたことが伺われます。
描かれているのは円錐、ゴブレット、半分に切ったレモン、ピッチャー、下の部分を切りとったタマネギ、紙、イースター・エッグ、カップ、聖餐杯、そしてサイコロですが、すべてテーブルの上にとウ感覚で並べられています。
レースのカーテンに描かれた模様はまるで刻み込まれたようであり、硬い質感を表現しています。
この作品を見た人は絵がキャンバスではなく、平坦な石の表面に描かれているように感じるかもしれません。
事実この作品は針金のフレームを埋め込んだ石膏板に描かれた後、深さのある木のフレームに入れられています。
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/483168