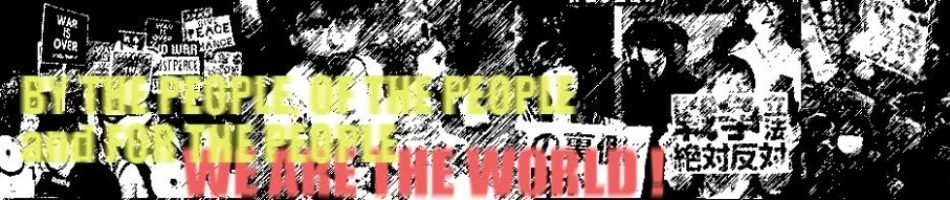
ホーム » エッセイ » 福島第一・ロボットが原子炉内の溶解ウラン燃料を最終的に確認《前篇》
人間が近づいたらたちまち死に至る程高いレベルの放射線の存在が、すべてを難しいものにしている
放射線に対し高い耐久性を持つ新型ロボットを投入し、所在と状況が不明の核燃料の特定を急ぐ
マーティン・ファクラー / ニューヨークタイムズ 2017年11月19日

その日福島第一原子力発電所内で4人のエンジニアが数台のモニターの前に腰を下ろし、中の1人がゲームコントローラのように見える装置を操作していました。
彼らはこれまでの一カ月間、今まさに行なおうとしていることのために訓練を続けてきました。
福島第一原発内の破壊された原子炉の中心部に一台の小型ロボットを送り込み、操作するためです。
福島第一原発内の破壊された原子炉内にはこれまでも調査用のロボットが送り込まれてきましたが、あまりにも高い線量の放射線や内部に散らばるがれきによって破損するなどしていずれも操作不能に陥りました。
しかし、ミニ・マンボウと呼ばれる新型は放射線に対する防御能力を高くし、さらに浸水した状態の原子炉建屋内にあるその部分だけ異常に放射線量の高いホットスポットを避けるためのセンサーも備えています。
シューズケースほどの大きさのミニ・マンボウは小型プロペラを装備し、小型ドローンが空中を飛行するのと同じ要領で水中を行き来します。

事故によって破壊された原子炉建屋内を3日間慎重に走査した後、ミニ・マンボウは最終的に最も損傷の激しい原子炉3号機に到達しました。
そして原子炉底面に開いた大きな穴、そしてその下の床に凝固した溶岩のような塊が存在する画像を送信してきました。
これは事故の際に溶融したウラン燃料について初めて撮影された画像になりました。
実際に使用される前に、ミニ・マンボウは横須賀でデモンストレーションを行いました。
放射線に対する耐久性の高い機体とセンサーを装備した水中ロボットです。
ミニ・マンボウは以前のロボットが失敗した場所で、残骸のある場所やホット・スポットを巧みに回避しながら、福島第一原発の事故現場で極めて危険な存在であるウラン燃料の所在を明らかにしました。
原子炉3号機ではすでに今年7月にも溶解した核燃料の一部と見られる物質の存在を遠隔操作のカメラを使って確認しており、日本政府の関係者は同様の成功を重ねていくことで、チェルノブイリ以降最悪となった原子力発電所事故の転換点になる事を望んでいます。

2011年3月11日に発生した巨大地震と15メートルを超える津波が福島第一原発の重要設備である冷却システムの破壊して福島第一原発の大惨事が発生しましたが、それ以来、溶解した核燃料はどこにどのような形で存在しているのかという問題は、最大の謎の1つとされてきました。
冷却機能を失った原子炉の核燃料は過熱状態に陥り、6基中3基でメルトダウンが発生しました。
ろうそくのろうが溶けるようにして液状化し、鋼鉄製の格納容器を溶かして穴を開けるほど高温化したウラン燃料は、下部のコンクリート製の基礎部分にも浸透して行きました。
これまでのところ、後に『フクシマ・フィフティ』として賞賛されることになった福島第一原発の職員たちが海水を原子炉建屋内に注入して再度原子炉の冷却を可能にするまで、核燃料が溶解してどこをどう通りどのような状態になってるのか、誰も状況を把握できずに来ました。
最大の原因はもし人間が近づいたらたちまち死に至る程高いレベルの放射線の存在であり、溶解した核燃料の状況など確認しようがありませんでした。

しかし東京電力の職員たちが事故現場の処理に習熟していくにつれ、行方不明の核燃料を探す余裕も出てきました。
科学者やエンジニアはミニ・マンボウのような放射線耐久型ロボットや、原子炉内部の放射線量の状況を調査するためマンボのような放射線耐性のロボットと、反応炉の内部を見るためにミュオンと呼ばれるエキゾチック空間粒子を使った巨大なX線走査装置も製作しました。
日本政府の原子力行政の担当者と原子力発電所を所有する各電力会社は、現場の技術者が溶解した核燃料の所在を特定したことにより国内世論が変わることを望んでいます。
福島第一原発の事故により関東北部から東北地方にかけて大量の放射性物質が放出されてすでに6年半が経過しました。
最悪の局面では東京も一時危機的状況に陥るかに見えましたが、現在は福島第一原発が事故直後の混乱を収拾して脅威が去ったことを世間に周知したいと考えています。
すなわち計画的に事故収束・廃炉作業を進めていると…。

東京電力の木元崇宏原子力・立地本部長代理が次のように語りました。
「これまでは、溶解した核燃料がどのような状態でどこにあるのか、正確には分かりませんでした。それが特定できたため、これからはそれを回収する計画に着手することができます。」
東京電力は現在、福島第一原発をひとつの巨大な産業事故処理現場と定義したいと強く望んでいます。
約7,000人が毎日作業を続け、新しい汚染水の貯蔵タンクを建設し、敷地内に散乱していた放射性廃棄物を新しい処分場に移し、巨大な水素爆発によって崩壊した原子炉建屋の上に巨大な足場を組み上げました。
敷地内への立ち入りも、1年前は特別性の放射線防護服を着用しなければなりませんでしたが、現在はもっと簡単になりました。
今日では労働者や訪問者は、最も危険な領域を除くすべての領域を街を歩くような格好で移動することが可能です。
東京電力の案内担当者によれば、これは中央部分にあった樹木を伐採し、敷地内をすべて再舗装して汚染を密閉したことにより可能になったと説明しました。
[写真下]現在の福島第一原発・1号機原子炉建屋。上部構造は2011年3月の事故の爆発により吹き飛ばされました。

《後篇に続く》
https://www.nytimes.com/2017/11/19/science/japan-fukushima-nuclear-meltdown-fuel
+ – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – +
福島第一原発の事故について改めてもっとも許し難いと思うのは、やはり160,000人とも250,000人とも言われる人々のそれまでの暮らしを葬り去った事でしょう。
人間は新たに幸せな暮らしを手に入れればそれですべて良しとするほど単純には出来ていないと思います。
私も年齢を重ねるごとに、自分の祖先がどうだったかという事を考えることが多くなりました。
過去とつながっているという事の価値は、漠然としか理解できないものですが、だからと言ってさほど価値が無いという事でもありません。
福島第一原発については物理的な回復に加え、人々の心の再生という事も大切な課題だと思っています。