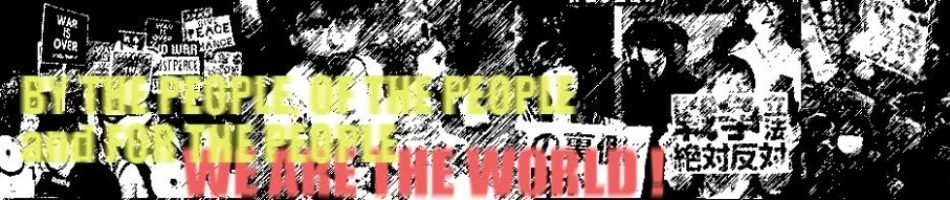
ホーム » エッセイ » 世界遺産・琉球文化の象徴、首里城が焼失
30年の労苦を積み上げて再建・琉球文化の粋を集めた宮殿が一夜にして灰燼に
併載 / 米国海兵隊記録写真集 : 焼失した首里城と沖縄戦の記録

I山口まり / AP通信 2019年10月31日
10月31日木曜日、沖縄県那覇市にある首里城で大火災が発生し、吹き上がる炎と煙が沖縄が誇る歴史的遺産をほぼ壊滅させてしまいました。
31日木曜日の早朝に発生した火災により沖縄の首里城が焼け落ち、ユネスコ世界遺産でもある同施設の主要な施設がほぼ壊滅しました。
沖縄県警察のスポークスマンによれば火災が発生して数時間が過ぎても鎮火せず消防隊が消化活動を続けており、近隣の住民は安全な場所に避難しました。
沖縄の県庁所在地である那覇市で発生した火災は、首里城の中心施設である正殿から始まりました。
先に正殿と北殿が焼失し、その後さらに3番目の主要施設である南殿、南側の寺院が焼け落ちました。

負傷者はいませんでした。
火災の原因は早い段階では明らかになっていません。
防護服をまとった消防署職員は現場のテレビインタビューで記者団に対し、警報を確認した民間の警備会社から火災の最初の通報があったと語りました。
正殿内のメインホール近くで発生した火災は、たちまち他の主要な建物に延焼しました。
NHKはオレンジ色の炎に包まれた首里城の施設が黒焦げの骨組みだけになり、地面に崩れ落ちる様子を伝えました。
現場には多くの住民が集まり、丘の中腹にある路上で心配そうに現場を見つめていました。
多くの人々が押し黙ったまま写真を撮影し、完全に崩れ落ちる前の首里城の様子を記録にとどめようとしていました。。中には涙を流している人々もいました。

「大切な象徴を失ってしまったように感じます。」
現場で緊急対応チームを率いていた那覇市長の城間幹子さんがこう語りました。
「衝撃を受けました。」
城間市長は、城にまだ残っているものを救うためにできる限りのことをすると誓いました。
菅義秀内閣官房長官は記者団に対し、日本政府は国立公園内の首里城再建のため最大限の努力をするつもりだと語りました。
首里城の再建を手伝った琉球大学の歴史学者である高良倉吉名誉教授は、火災の場面を見たときに言葉を失ったと語りました。
彼はNHKの取材に、城の再建は太平洋戦争末期の沖縄戦で失われた沖縄の人々の歴史と琉球文化の遺産を復元するために行われた記念碑的事業であったと語りました。
「まだ現実として受けとめることができません。」
高良名誉教授がこうかかりました。
「首里城の再建には30年以上の時間がかかり、多くの人々の知恵と努力の結晶でした。首里城は建物だけでなく、内部の設備も含め細部にわたる全てを再構築したものだったのです。」
オリジナルの首里城は1429年から日本に併合される1879年まで450年間続いた琉球王国の沖縄文化遺産の象徴となるものでした。

そして首里城再建は第二次世界大戦の沖縄戦から復興に向けた苦闘と努力の象徴でもありました。
首里城は20万人の島民が殺された1945年の沖縄戦で焼失しました。
死んだ沖縄県民のほとんどは民間人でした。
首里城は1992年に国営沖縄記念公園の一部として大部分の修復が完了し、2000年にユネスコの世界遺産に指定されました。
沖縄は日本が完全な独立を取り戻してから20年が過ぎた後の1972年まで米国の占領下にありました。







+ - + - + - + - + - + - + - +
首里城の焼失については何とも痛ましい限りという言葉しか浮かんできません。
再建にかけた30年間に及ぶ労苦が一夜にして文字通り灰燼に帰してしまった喪失感はいかばかりかとも思います。
第一報を聞いた瞬間は最低の馬鹿者が『放火したのか?!』とも思いましたが、現時点でそうした物証も傍証もないようです。
この上は関係者の方々にとっては大変な労苦かもしれませんが、一般市民の募金も合わせ、日本国民が心を一つにして再びの再建を目指すしかないと思います。