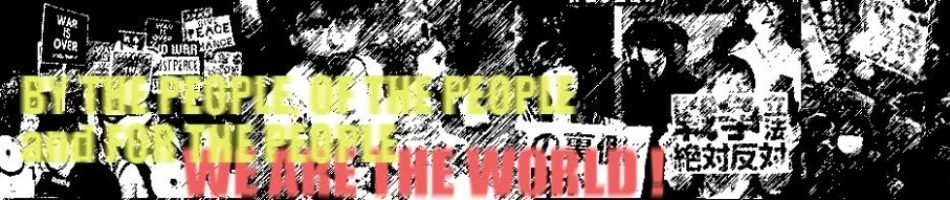
一般市民が創り出す価値にこそ多数にとっての利益があり、共有することができる善意がある
世界は自由で公正でなければならないという信念があってはじめて、人類に貢献できる報道が可能
これまで私たちが知っていた世界の枠組みは、すでに崩壊してしまっている
キャサリン・ヴィナー / ガーディアン 2017年12月8日

ガーディアンの歴史に残る深刻な間違いの1つは1948年に起きました。
今日の状況からは考えられないことですが、マンチェスター・ガーディアンは英国国民健康保健の設立にはっきりと反対の立場をとったのです。
ガーディアンは保健制度の確立を 『大きな進歩』として支持する一方で、国家が福祉を提供することには「才能のない人の割合を増加させる危険性がある」という懸念を表明しました。
3年後、ガーディアンはこうした立場をさらに進め、1951年の総選挙で保守党を支持しました。
一連の動きについて歴史家は、当時の編集者A.P.ワーズワースが福祉国家構想の背後にいた情熱的な労働党の政治家であるナイ・ベーバンを嫌っていたため、こうした決定が行われたと確信しています。
何か難しい問題の真っ只中にあるときに、たとえ個人的なポリシーとビジネス上での利害の対立を回避できたとしても、政治的に適切な解釈と判断をする事は簡単な事ではありません。

ニュース組織はときには事態を悪化させる方向に向かわせることがあるかもしれません - それらを正しい方向に向かわせるためには、正義を貫こうとする価値観と原則が必要であり、それによって事態は前に進むことになります。
ガーディアンの根幹を成すこうした中心的価値の多くは、1921年に創刊100周年を迎えた際に急進的な自由主義者であった編集長スコットによって定着させられたものです。
スコットはこう記しました。
「コメントは自由だが、事実は侵すべからざるものである。」
そしてガーディアンの価値観を次のように整理しました。
すなわち、正直、潔癖(誠実)、勇気、公平性、読者への責任感、そして地域社会への責任感です。
ジョン・エドワード・テイラーの創刊の際の宣言同様、C.P.スコットのエッセイは力強く希望に満ちています。
スコットはこうも書いています。
「新聞は物質的な存在であると同時に倫理観を持っている。」

テイラーとスコットによって成文化されたガーディアンの倫理的な信念は、人類が長い時間をかけて人間世界を理解し、そしてそれをより良いものにしてきたという確信に基づくものです。
ガーディアンは一般市民が創り出す価値を信じています。
そこには多数にとっての利益があり、共有することができる善意があります。
私たちすべてが平等な価値を持っています。
そして世界は自由で公正でなければなりません。
こうした啓示にあふれた考え方はガーディアンの根幹をなすものであり、マンチェスター・ガーディアンから1959年にガーディアンに題号が変わっても保たれてきました。
ガーディアンのステークホルダーはスコット・トラストだけです。
ガーディアンが産み出した富は、すべてジャーナリズムのために費やされなければなりません。
そしてオブザーバー紙ももちろん、独自の名誉ある歴史と展望を持っています。同じ企業グループの一翼として私たちは兄弟のようなものですが、双生児と言うほど似ているわけではありません。

大きな歴史的な事件に遭遇した都度、世界は自由で公正でなければならないという信念に支えられた報道こそがガーディアンの歴史を作ってきました。
独自の立場に立ったスペイン内戦の報道、世界を驚かせたエドワード・スノーデンの内部告発、スエズ危機の際の反植民地支配宣言、ルパート・マードックのメディア支配に対する抵抗、警察や政治家による電話盗聴スキャンダルにも立ち向かいました。さらにはジョナサン・エイトケンを結果的に刑務所に送りこむことになった報道、そしてパナマ文書の公開など、反権力の立場を一貫して貫いてきました。
これらの価値観、ポリシー、アイディアは確立されたものとなり、揺らぐことなく続いてきました。
しかし価値観やポリシーなど、それ自体は新しい時代の道徳体系が激変するという状況にどう対処すべきかを教えてくれるわけではありません。
これまで私たちが知っていた世界の枠組みはすでに崩壊してしまっており、ジャーナリストとして一市民として、これまでの価値観やポリシーやアイディアをどうやって維持して行けば良いのか、改めて問い直さなければなりません。
そしてこれまでの価値観やポリシーやアイディアが、将来に渡っても私たちの報道姿勢や報道目的を人々に伝えることが出来るのかという事も。
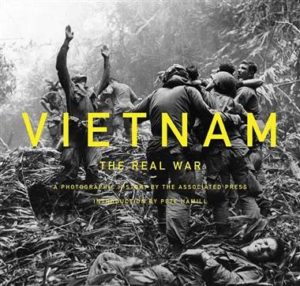
権力の無法な介入を招いたピータールーの公開会議が開催されてから約200年が経過しました。
しかし1989年に世界規模のウェブの仕組みが発明されて以降の30年間は、ジョン・エドワード・テイラーやC.P.スコットが想像も出来ない方法で世界の価値観を一変させてしまいました。
この技術革新は刺激的で劇的なものでした。
600年前にグーテンベルクが印刷技術を発明してマスコミュニケーションが確立され、支配階級と経済的な強者によって情報源は支配されてきましたが、ウェブ時代の到来はや多くの人々にとって新鮮な空気の息吹のように感じられたはずです。
World Wide Webシステムを考案したティム・バーナーズ・リーは、
「これはすべての人々のためのものです。」
と語りました。
始まりはスリリングなハイパー接続世界 - いつでも瞬時に誰とでもつながることが出来る時代の到来は、誰でも指先一本で世界中に散らばっている情報にアクセスして、何でも解決してくれるように感じました。
参加することはきわめて簡単で、誰もが助け合うことが出来る、理想社会の広場のようなものでした。

多くの報道機関はインターネットを古い権威を脅かす存在とみなしました。
しかし1995年から2015年までガーディアンを率いたアラン・ブリッジャーのような先見的な編集者はこうした技術革新がジャーナリズムの新たな可能性を開くものと判断してデジタル技術に積極的に投資し、この分野の技術者やプロダクト・マネージャーなどを新たに雇い入れました。
これは新しい世界のジャーナリストたちは、読者から積極的な提言と議論を受け入れる開かれた場所で仕事をすべきだとの認識に基づくものでした。
こうしてガーディアンはイギリスの報道機関として初めて一般読者から編集者を採用し、それまでのトップダウン方式の伝統的新聞解説モデルを逆転させたオピニオン・サイトを立ち上げました。
こうしてアラン・ブリッジャーはガーディアンをデジタル革新の最前線に置き、これまでとは全く違う読者や市民との間に新しい時代の関係を築きました。
4年前、私が『読者たちの台頭』というエッセイの中で述べたように、開かれたWeb環境は真に新しいジャーナリズムの可能性を創り出しました。
そしてWebによる技術革新を否定したジャーナリストたちは、自分自身の利益のみならず質の高いジャーナリズムがもたらすはずの恩恵のその両方を損なってしまうことになったのです。
《4》に続く
https://www.theguardian.com/news/2017/nov/16/a-mission-for-journalism-in-a-time-of-crisis
+ – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – +
今回の翻訳は、この【星の金貨】にとっても存在意義を問い直す良い機会になりました。
真実を淡々と伝えられて初めて、社会は正しい方向に向かうことができます。
しかし今の日本ではその多くが、一般国民の『多数派』の意思を向かわせる方向があらかじめ決めてある『操作性重視』の報道のように見えます。
それを『報道』と呼んで良いものなのかどうか…
しかも日本の報道のシステムには、この記事で語られているような信念を持ったフリーランスのジャーナリストたちを排除する仕組みまで作られています。
この記事の本分中にある
『ガーディアンは一般市民が創り出す価値を信じています。
そこには多数にとっての利益があり、共有することができる善意があります。』
という概念とは、まさに正反対の報道システムが幅を利かせているのが日本です。
たとえばNHKのような『公共放送』は、政治が本当に市民の利益を最優先に進められているかチェックしなければならないはずなのに、現状は国策の宣伝と浸透を最優先しているように見えます。
それによって日本は何を現実のものにしようとしているのでしょうか?
権力者の思い通りの現実になるように最大規模の報道機関が露払いするようでは、太平洋戦争以前の日本となんら変わりません。
どころか、世界における民主主義の発展と対照的な『退化』すすめる原動力になってしまっていると言わなければなりません。