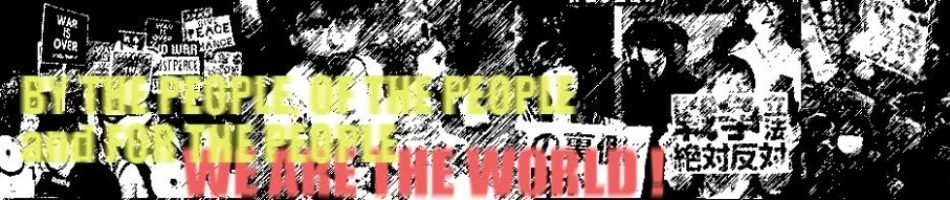
ホーム » エッセイ » 『一票の格差』自民党議員を大量当選させる日本の選挙区の線引き
日本国内の自治体の4分の3が今後数年で消滅 - 日本の少子高齢化も自民党選挙の追い風
日本の少子高齢化は地方の比較的高齢で保守的な地域の『一票』の政治的な力が強くなることを意味する

エコノミスト 2019年11月14日
今年7月に実施された参議院議員選挙には「著しい不公平があった」、北海道の札幌高裁(冨田一彦裁判長)は10月にこう判決を下しました。
さらに悪いことに、参議院議員選挙は「違憲状態」で実施されたものだとの判断も示しました。
彼は日本の深刻な議員定数の不均衡な配分についても言及し、その原因は人口が著しく異なるのに「都道府県を各選挙区の単位とする仕組みが原則とされていることにある」と指摘しました。
宮城県では参議院議員として当選するためには有権者約976,000人の票が必要でした。
これに対し福井県では326,000人分の票を獲得できれば参議院議員になることができたのです。
この事実が意味するところは、福井県人は宮城県人と比較して約3倍の数の自分たちの利益代表者を国会に送り込むことができるということです。
こうした格差は衆議院においてはそれほど悪くはありません。
もっとも最も人口の東京の選挙区と比べ、人口が最も少ない上その多くが田園地帯の鳥取県との格差は約2倍にとどまっています。

国政選挙の選挙区の線引きをどうすべきかという点に関し、日本国憲法の規定は少々漠然としすぎており、「すべての人々は法の下で平等」であり、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と述べるにとどまっています。
選挙区の設定をどうすべきか、日本でその具体的権限を有するのは国会自身です。
選挙区の不公正を正そうと取り組む弁護士たちは裁判所において、これらの法の下での平等を保障する日本国憲法の条項を繰り返し使用し、議員定数の不均衡な配分に異議を唱えています。
札幌高裁で10月に判決が示された訴訟の原告団を率いるのは升永英俊弁護士です。
升永弁護士が見解を示した通り、「一部の地域の有権者は一人が0.5票の権利しか持たない」日本の現状は確かに民主的とは言えません。
日本の裁判所は議員定数の不均衡な配分は憲法に違反するという判断を繰り返し示しましたが、そこで行われた選挙の結果については無効とすることはしませんでした。
その代わり裁判官は、衆議院議院選挙について人口密度の高い低いによって生じる格差は2倍以下に保たれなければならないという原則を確立しました。
しかし参議院議員の場合はその格差は約3倍にまで拡大しています。
国会はこの原則に適合させるために、選挙区の境界を繰り返し調整しました。
しかし議員たちは、日本の47都道府県それぞれが衆参両院において最低1人の国会議員がいるべきであるという考えを放棄することには消極的です。

選挙区への議員定数の配分は多くの民主主義国において問題になっています。
アメリカの憲法では、人口に関係なく各州に2人の上院議員を割り当てています。
その結果ワイオミング州には290,000人の住民に1人の上院議員がいますが、カリフォルニア州は2,000万人に一人です。
マレーシアの昨年の国会議員選挙では最大で8倍という格差が生じました。
日本では裁判所の判断が重視されるようになり、それ以来議員定数の配分の格差は著しく縮小しました。
政治学者の菅原 琢博士はかつては参議院の上議員定数の配分格差は6倍だったと語りました。
しかし現在、世代別人口構成が極めて特異な状況になってきた日本では、議員定数の不均衡は相変わらず深刻です。
国全体では人口が減少しているにもかかわらず、東京などの大都市圏だけは成長を続けています。
大都市圏から離れた一部の県では、大都市圏の増加と同じ割合で人口が減少しています。
東京大学のマッケルウェイン・ケネス・盛教授は、日本の議員定数の不均衡は次の選挙が始まるまでに裁判所によって設定された制限を再び超えることになるだろうと予想しています。
北海道の人口は今後20年間で3分の1減少すると予測されています。
さらに日本国内の自治体の4分の3が今後数年で消滅する可能性があるとの予測をシンクタンクである日本政策会議が明らかにしました。
こうした自治体の領域は広大で日本の国土の20%を占めていますが、人口はわずか4%に過ぎません。
これらの地域から選出される国会議員はこれまで以上に広大な地域を代表することになります。
それにより、日本の人口構成の変化によってすでに取り残されていると感じている有権者と接触する機会がますます少なくなることを意味しています。
さらに農村部の人口の急速な減少は、大都市の『一票』を犠牲にしつつ、地方の比較的高齢で保守的な地域の『一票』の政治的な力が強くなることを意味します。
これにより今後選挙区の線引きは日本の人口の急速な少子高齢化によって、急速に偏ってしまうことになるでしょう。

このことは都市部よりも農村部での支持が強い与党自民党に有利に働きます。
自民党は現在国会を支配しており、与党国会議員が大規模な選挙制度改革を受け入れたがらないのは当然です。
こうした状況を見て、升永英俊弁護士をはじめとする原告団は「国政選挙の一票の格差」についての訴訟に踏み切ったのだと語りました。
札幌訴訟に関わった奥山倫行弁護士は、次のステップはこの訴訟を最高裁判所に持ち込むことだ語りました。
「一人一票こそが民主主義の前提条件なのです。」
+ - + - + - + - + - + - + - + - +
[アベ政治]については、SNSを見ればまるで数々の罪業が列挙されている様相を呈しており、今さらここで何を書くべきこともありません。
「1日も早くアベ政治を終わらせよう!」
それだけです。
ただこの記事で紹介されている、一票の格差について戦っておられる弁護士さんたちには敬意を表さなければなりません。
さらには北海道の人口が3分の2に減ってまう、あるいは日本国内の自治体の4分の3が今後数年で消滅する可能性があるなどという、わきめて深刻な実情について、なぜ日本の報道は真剣に取り上げないのだろうという?
という疑問も残ります。
この問題だけ見ても、憲法の改定などより『今、取り組まなければならない』問題が山積していることを痛感させられます。